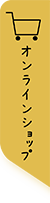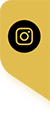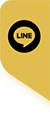雨が多く降る6月の植物を紹介します。
紫陽花(あじさい)
日本原産の落葉低木で、梅雨どきに咲く代表的な花木です。
真の藍色の花が集まるという意味の「集(あず)+真(さ)+藍(あい)」が変化し、紫陽花になったと言われています。花びらのように見える部分はガク片が変化したもので、土壌の酸度によって色が変化する特徴があります。
また、古くから6月に紫陽花を軒下に吊るしておくと魔除けになると言われています。
三重県津市の「かざはやの里」では、約33,000平方メートルのエリアに、約40品種77,700株の紫陽花が咲きます。

花菖蒲
初夏、梅雨の中でも、ひときわ華やかに咲き誇る多年草です。
野生のノハナショウブをもとに、江戸時代を中心に数多くの品種が育成され、現在2,000以上あるといわれています。古くから優美な花形としっとりとした風情が魅力で観賞用として楽しまれています。色彩の魔術師とも呼ばれるように、花色の変化に富んでいます。
古くから艶やかな花姿が花色の変化に富んでおり、花被が大きく発達するのが特徴です。
伊勢神宮外宮のまがたま池の畔には14,000株の花菖蒲が美しく咲き誇ります。
露草
梅雨が明けてしばらくすると、土手の斜面や道端に可憐な青紫色の花を咲かせます。
加賀友禅では、「青花」と呼ばれる露草の花の汁を用いて線を写し取ります。青花は後工程で水ですすぐと跡形もなく消え去るからです。
桔梗(ききょう)
秋の七草のひとつで、万葉の時代から観賞されている花です。
「岡に咲く神草」の意味で、別名オカトトキ(岡止々支)ともいいます。また、木偏を取ると「吉が更に」という意味にも捉えられることから縁起がよいとされ家紋としても用いられています。
日当たりのよい草原に見られますが、最近はこのような場所が減ったため絶滅危惧種になっています。根は漢方薬にも利用されます。
バラ
5~6月はバラが美しく咲き誇る季節です。品種改良が進められており、現在の品種数は4万以上と言われています。花言葉も色や花以外の部位、バラの状態や本数、組み合わせなどで異なります。
おかげ横丁のすぐ近くにある神宮会館には「神宮ばら園」があり、春と秋に150種、450株のバラが咲き誇ります。