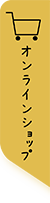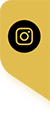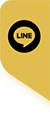二十四節気は11月7日から立冬、11月22日からは小雪です。
立冬は、冬の気配を感じるころです。2025年は富士山の初冠雪もすでに観測されています。
小雪は、北国では雪がちらつきます。
伊勢神宮の祭典・その他の行事
11月23日
新嘗祭(にいなめさい)
天皇陛下が皇居において、新穀を天神地祇に捧げ、感謝の報告を行い、神から贈り物として自らも召し上がります。また、「しんじょうさい」とも言われ、「新」は新穀を「嘗」はお召し上がりいただくことを意味しています。
神宮では神嘗祭で新穀が奉られるため、新嘗祭はありませんでしたが、明治5年に勅使が差遣されて行われたのが始まりです。
おかげ横丁では、新酒を奉納いたします。

11月30日
大祓
12月煮る大きな祭典「月次祭」を前にして大宮司以下神職、薬師を祓います。
12月1日
御酒殿祭(みさかどのさい)
月次祭に大御饌のための御酒が麗しく出来るように祈るとともに全国酒造業者の弥栄を祈ります。
伊勢神宮では、白酒・黒酒・醴酒(れいしゅ)・清酒の4種が供えられます。
11月2日
旧亥の子の日
亥(猪)は火を司る水の気とされ、この日に炬燵開きすれば火事にならないとされています。茶道では、畳に切った炉を使い始める炉開きの日です。
中国には、旧暦10月の亥の日に七色の餅を食べると無病息災に暮らせるとの言い伝えがある「亥の子餅」があります。これが日本に伝わり、白、赤、黄、栗、胡麻の五色の餅を食べる行事が一部に残っています。また、猪の多産をあやかるお菓子ともされています。
11月15日
七五三
三代将軍徳川家光が、虚弱であった四男徳松お祝いをするために始めたと言われています。三歳で髪を伸ばし、五歳で袴を身に着け、女の子は七歳で帯を締めます。
七五三に欠かせない千歳飴は、浅草で紅白に染めた棒状の飴が千年と言う名で売られたのが始まりです。
おかげ横丁でも七五三をお祝いする家族が見られます。
植物・自然
水仙やツワブキ、山茶花などの花が咲き始めます。
また、ヒラメやクエ、牡蠣、ほうれん草など冬は食べ物が豊富な季節です。

旧暦10月は神無月です。神様が出雲の国に集まりますが、伊勢の神様は特別な存在なので、出雲へは行きません。
神様が出雲に行っている間は、恵比寿様が地域をお守りしています。
2024年11月7日
公益財団法人伊勢文化会議所 五十鈴塾 季節の講話より