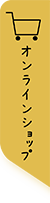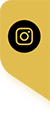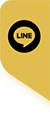伊勢神宮のほど近く、おかげ横丁の一角にたたずむ木造の建物「すし久」。

その歴史ある空間で、毎月晦日の夜に開かれるのが「みそか寄席」です。三十余年の間、月の終わりに変わらず続けられてきたこの落語会が、2025年7月、ついに400回目という節目を迎えます。
みそか寄席が始まったのは、平成三年のこと。
伊勢を訪れる方々を、笑いでもてなしたいという想いから、地元・松阪市出身の落語家・桂文我さんを主宰に始まりました。それ以来、三十四年にわたって多くの人々に笑いだけでなく「伊勢で落語に触れる特別な時間」を届けてきました。

会場となる「すし久」は、明治四年に建てられた木造建築をもとに、平成元年に復元された建物です。吹き抜けの梁には、明治二年の遷宮時に伊勢神宮から下賜された宇治橋のけやき材が使われており、寄席の場にも落ち着いた気品が漂います。
そんな趣ある空間に、毎月の晦日だけ現れる寄席は、まさに伊勢の隠れた風物とも言えます。
高座には、桂文我さんをはじめ、関西・関東を問わず実力ある噺家たちが登場します。古典落語から新作落語、大喜利まで毎回違った味わいの演目が用意されており、客席には自然と笑いが広がります。地元の方も観光で訪れた方も、親しみやすい語り口に耳を傾けるうちに気づけば寄席の世界に引き込まれてしまう、そんな魅力があります。

これまでの節目の回には、桂米朝さん、桂春團治さん、桂枝雀さん、柳家小三治さんといった名人たちが高座を務めてきました。
決して大きな舞台ではありませんが、長年地道に続けてきたことへの信頼と尊敬が、こうしたかけがえのない出演者たちをこの寄席に導いてきたのだと思います。
主宰の桂文我さんは、年間300回以上の高座に立つ、松阪市出身の落語家です。全国各地で活躍される一方で、生まれ育った三重への思いはとても深く、みえの国観光大使や松阪市ブランド大使としても地域に貢献されています。
伊勢のみそかを彩る笑いのひとときを届ける「みそか寄席」は、コロナ禍によって何度か中止を余儀なくされながらも、地域の方々と、この場を愛するお客さまの存在に支えられ、400回を迎えることが出来ました。
今後も回を重ねながら、伊勢の地とともに、落語の灯をつないでいきたいと思います。

400回という節目を迎えた今、改めてこの寄席の歩みに耳を傾けてみてはいかがでしょうか。笑いのなかに息づく土地の記憶と人の想いが、きっと心に残る時間をつくってくれるはずです。
>みそか寄席400回記念公演