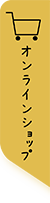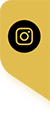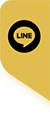寒い日が続いていますが、二十四節気の立春を過ぎると、暦の上では春と呼ばれる2月の花を紹介します。
梅
梅は、その年のどの花よりも早く咲くことから「百花の魁(さきがけ)」や「花の兄」と呼ばれています。また、春の訪れを告げる代表的な花から「春告草」の別名もあります。
花は、春の歩みのように一輪ずつゆったりと咲いていきます。見た目も美しく香りも高く、果実は食用となります。平安時代の初期までは、花見といえば梅を指していました。
節分草
節分の頃に咲くことからこの名前が付いています。
足元付近に白い花弁のような萼片を5枚開きます。ときに大群落を形成し、一面に白い花を咲かせる「春植物」ですが、現在は環境の変化や乱獲などによって種として少なくなり、見ることができなくなりつつある花です。
白い花が主流ですが、黄色い花を咲かせるキバナセツブンソウ(黄花節分草)という品種もあります。
柊(ひいらぎ)
名前の由来は、ヒリヒリ痛む、ずきずき痛む、うずくという意味の「疼ぐ」で、鋭いトゲを持つことから古くから魔除けとして用いられてきました。
節分の日には、鬼が嫌がる臭いのイワシと組み合わせて、鬼が家に入って来ないようにする「柊鰯」という風習もあります。一方、ヨーロッパではクリスマスの時期に窓辺や玄関に飾る風習があり、現代でもクリスマスの装飾としてヒイラギが使われています。
常緑樹であることから、冬の寒さの中でも緑に輝く姿が永遠の命の象徴となり、縁起のいい植物として庭木としても用いられています。

トベラ
樹木全体に臭気があり、節分の魔除けとして戸口に掲げられていた風習から「扉(とびら)の木」「扉」と呼ばれるようになったと言われています。初夏に咲く白い花は爽やかな香りがします。秋には鮮やかな真っ赤な種ができます。
チョコレートシンゴニウム
表のアンティークカラーのグリーンと裏の綺麗なボルドーの葉色。まるで葉色がチョコレートのような見た目から「チョコレートシンゴニウム」という名前がつきました。色だけでなく、形はハート型のようにも見えます。美しい模様の入った矢じり形や鉾形の美しい葉姿は魅力的で、バレンタインの贈り物にもピッタリです。